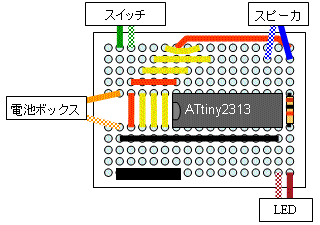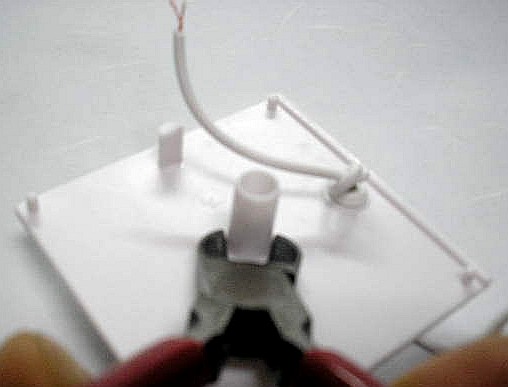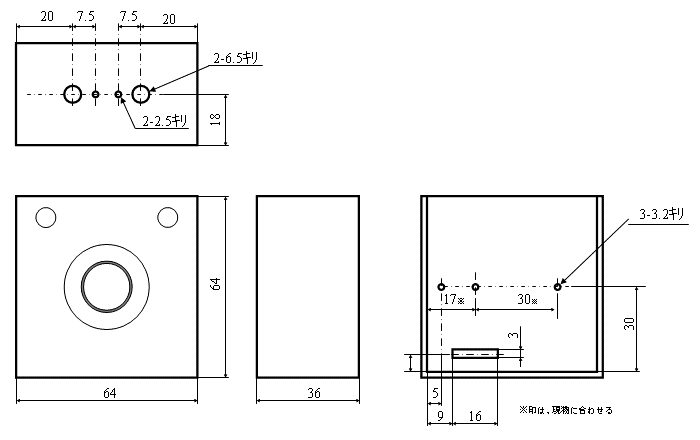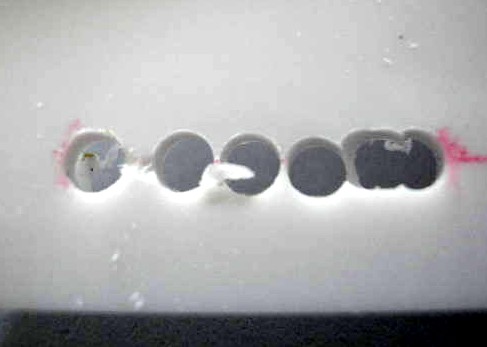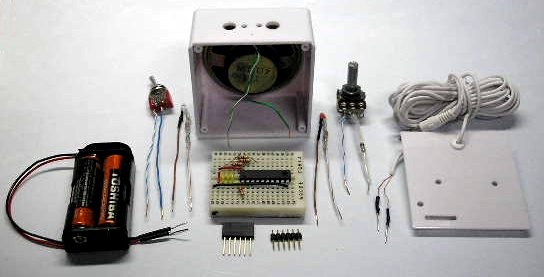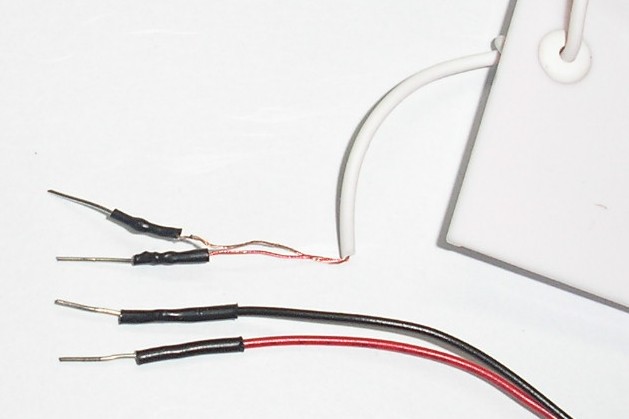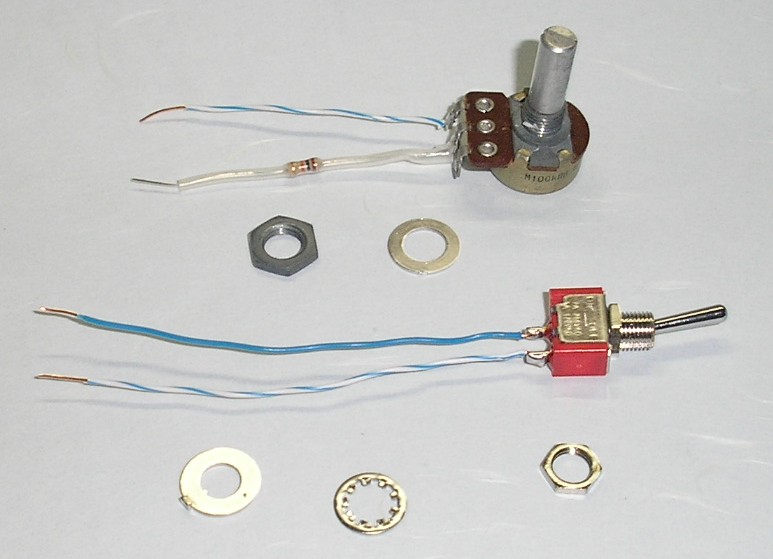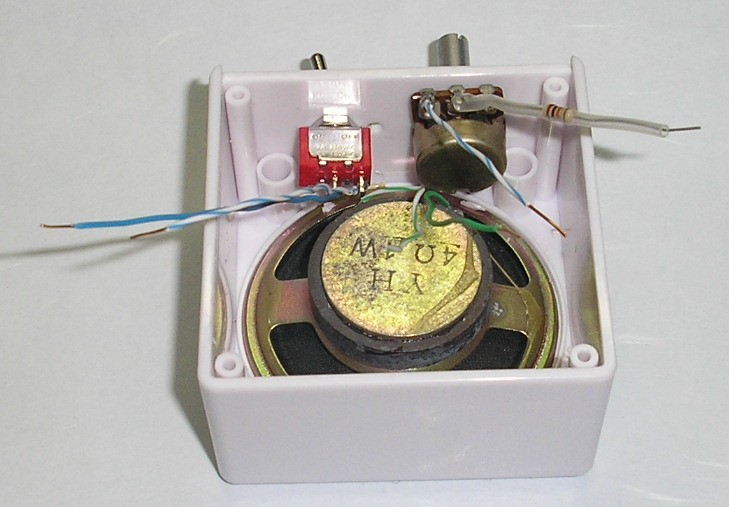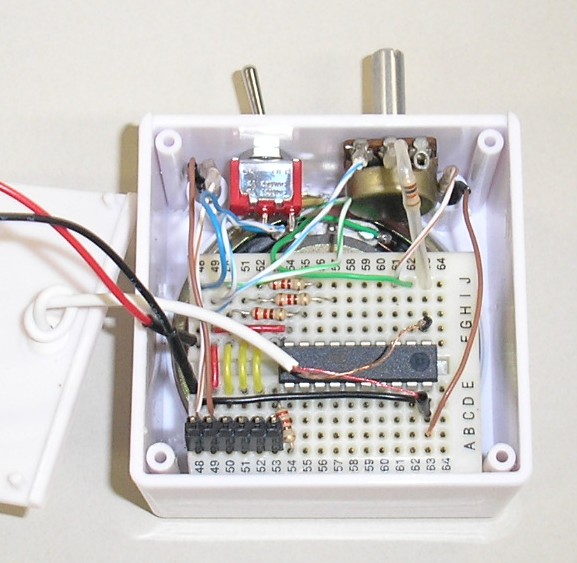◆コンパクトなスピーカボックスにマイコンをセットしてみました。
◆100均の小型スピーカ※を使って「電子オルゴール」を作りました。
中には、ミニのブレッドボードとAVRマイコン(ATtiny2313)などを使って、短時間で組み立てられるようにしました。
※スクエア型 耳もとスピーカ(発売元:丸七株式会社、新潟県)
■いろいろなセンサ付オルゴール
- ◆タイマーオルゴール…時間の設定が数種類できるオルゴール
- ●1つのディップスイッチで、2種類の時間設定ができる(例)3分計、5分計
- ●2つのディップスイッチで、4種類の時間設定ができる(例)1分計、3分計、5分計、10分計
- ●3つのディップディップで、8種類の時間設定ができる
- ◆警報オルゴール
- ●防犯警報オルゴール…ドアや窓が開くと鳴るオルゴール(リードスイッチを利用)
- ●水警報オルゴール
- ●満水警報オルゴール…お風呂などの水が一杯になると鳴るオルゴール
- ●渇水警報オルゴール…植木鉢が乾くと鳴るオルゴール
- ●明暗警報オルゴール(CdSセルを利用)
- ●目覚ましオルゴール…明るくなると鳴るオルゴール
◆実態配線図
今後の展開
・卒業記念品(電子オルゴール付写真立て)
・卒業記念品(電子オルゴール付アルバム)
◆スピーカボックスの加工
- ●オルゴールのみの実態配線図
- ●センサ付オルゴールの実態配線図
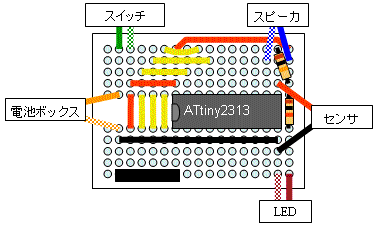
◆部品加工
- ●スピーカボックスの裏ぶたのあけ方
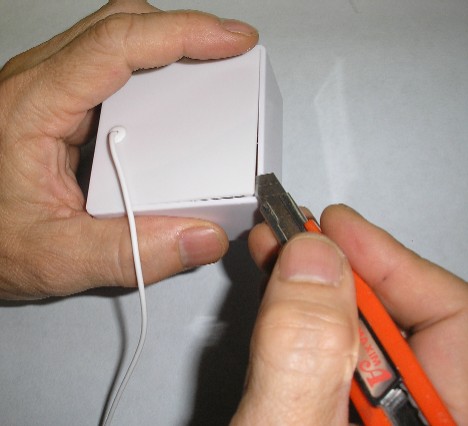 裏ぶたは接着剤で止めてあるので、カッタナイフを使ってすき間にこじ入れ、徐々にすき間を広げるようにする。
裏ぶたは接着剤で止めてあるので、カッタナイフを使ってすき間にこじ入れ、徐々にすき間を広げるようにする。
接着剤が付いてないところがある場合は、そこからこじ入れはじめるようにする。
- ●スピーカボックスの取り付け済みのケーブルをはんだごてを使ってはずす。
- ●不要部を切り取る
- ●スピーカボックスの製作図
※電池ボックス(単3×2本)の形状によっては、取り付け穴の位置は現物合わせする。
- ●スピーカボックスの穴あけ加工
製作図をもとに、穴をあける。
四角い穴は、φ3のドリルで穴をあけ、カッタナイフや精密やすりで仕上げる。
◆組立
- ●センサ付オルゴールの部品
- ●ブレッドボードへの部品の差しこみ
参照(ジャンパー線の製作)
- ●より線の単線化処理
参照(単線化処理)
- ●LEDの処理
参照(絶縁化処理)
- ●トグルスイッチ、ボリュームへ単線、抵抗の取り付け処理
ボリュームの片方に10kΩの抵抗をはんだ付けし、熱収縮チューブを被覆し、絶縁する。また片方には単線をはんだ付けする。参照(絶縁化処理)
- ●スピーカへ単線の取り付け処理
◆プログラムの書き込み
- ●トグルスイッチ、ボリュームを取りつける。
- ●ブレッドボードを取りつける。
- ●全ての配線を取りつける。
- ●HIDaspxを接続する。

- ●「アップロード」ボタンを押し、プログラムを書き込む。